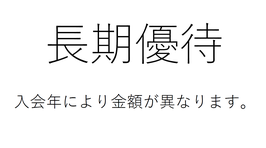歴史上の人物を踏まえた「禅と日本文化」(鈴木大拙著)講読会
鈴木大拙の名著「禅と日本文化」を古典翻訳家の水野聡先生とともに読み進める講読会です。
難解な内容を、水野先生が分かりやすく解釈し、仲間とともに読むことで新たな気づきや深い理解を得られます。
「中世、鎌倉期以降、日本独自の文化が醸成され、800年かけて現代の日本人がよいと思うもの、日本の美が形づくられてきました。その成り立ちには、歴史的な背景、仏教の背景、精神的な支柱として禅がある。本書を通して、日本の文化、美を感じ取る上で必要な背景を知ることができます。一冊読了したい、完走したいという方、ご興味ありましたら後期もご参加ください(水野聡 談)」。
後期は第4章~第7章の「禅と剣道」「禅と儒教」「禅と茶道」「禅と俳句」を読みこみます。
禅僧と楠木正成による一剣問答などから、剣術と禅の深い相関関係を読み解き、中国から入ってきた茶の湯がいかにして茶道に発展したのかを知り、悟りと宇宙的無意識を考察し、直感、直覚、孤絶、風雅といった禅の精神と俳句の不可分の関係を読み取ります。
人気講座のZoomが初回無料
本講座は、2022年2月に開始し、好評のうちに7月で前期を終えました。
後期(2022年8月~2023年1月)の募集にあたり、第8回8月23日のZoom授業に無料参加できる特典をつけます。お申込はページの下記からお待ちしています。
2022年後期 スケジュールと各講座のテーマ
全日程、13時~14時30分。内容により、15時まで延長することがあります。
| 日程 | トピック |
| 第8回 2022年8月23日(火) | 第4章 禅と剣道① |
| 第9回 2022年9月27日(火) | 第4章 禅と剣道② |
| 第10回2022年10月25日(火) | 第5章 禅と儒教 |
| 第11回2022年11月22日(火) | 第6章 禅と茶道① |
| 第12回2022年12月13日(火) | 第6章 禅と茶道② |
| 第13回2023年1月24日(火) | 第7章 禅と俳句 |
受講料【後期6回】
IJCEE会員 7,700円
フレンドシップ団体 TJスクール生 9,400円
一般 10,800円
※本講座は昨年度、受講料1回あたり2,800円として実施いたしました。今年度は、長引くコロナの影響で収入が少ない方々に配慮し、受講料を引き下げています。
受講形態/催行最少人数
【受講形態】
①会場受講(機械振興会館)
②Zoom受講
③録画動画受講(2022年後期授業は、2023年7月末まで配信いたします。
【催行最少人数】各講座 7名
受講申込をしたすべての方に、Zoomリンクと見逃し配信をいたします。
会場受講、Zoom受講など、ご都合に合わせて回毎に変更可能です。
使用テキスト
メインテキスト
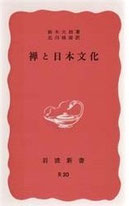
「禅と日本文化」
鈴木大拙 著 北川桃雄訳 岩波新書800円
*各自ご購入下さい。
鈴木大拙プロフィール
仏教(禅)学者、思想家(1870~1966)。
石川県金沢市に生まれる。東京帝国大学に学び、鎌倉円覚寺で修行する。1897年より渡米、以降アメリカの大学やヨーロッパで大乗仏教思想、とくに禅思想を広く世界に紹介し、海外に“ZEN”ブームを引き起こした一人となる。『禅と日本文化』をはじめ、著書約100冊の内23冊が、英文で書かれている。梅原猛曰く、「近代日本最大の仏教学者」。
講座の進め方
●世界的名著である、鈴木大拙の『禅と日本文化』を講師の指導の下、音読していく講読講座です。※講読対象は訳文(日本語)です。
●講座受講生はテキストの指定章段を事前に目を通して予習しておく。研修当日、任意の受講生による音読の後、水野講師がわかりやすく解説して進めます。講座はijcee事務局での座学に加え、遠隔地からもZOOMを通してリアルタイムで受講できます。またすべての受講生に見逃し配信をいたします。
参加者全員で「禅とは何か」「日本文化とは何か」を現代の生きた知識として共有していきましょう。
参考テキスト
上記、「禅と日本文化」の対訳本がこちら
・対訳「禅と日本文化」
Zen and Japanese Culture 講談社
また、下記書籍でも「禅と日本文化」について分かりやすく解説しています。
NPO日本文化体験交流塾発行
見逃し配信スケジュール
|
講座実施日 |
見逃し配信開始日 |
|
第1回2022年8月23日(火) |
2022年8月30日(火) |
|
第2回2022年9月27日(火) |
2022年10月4日(金) |
|
第3回2022年10月25日(火) |
2022年11月1日(金) |
|
第4回2022年11月22日(火) |
2022年11月29日(金) |
|
第5回2022年12月13日(火) |
2022年12月20日(金) |
|
第6回2023年1月24日(火) |
2023年1月31日(金) |
2022年2月~7月【前期7回】の講読会を動画で振り返る
2022年の前期では、「禅と美術」「禅と武士」をじっくり読み解きました。
後期の授業の前に、前期のおさらいをしたい方、動画で前期7回を振り返ることができます。
ページ下記のカートよりお申込みいただけます。
2022年実施済み
|
|
|
日程 |
本年度企画 |
昨年度2021年実施 |
講師/備考 |
|
前期 |
第1回 |
2/1(火) |
事前説明「鈴木大拙を学ぶ」 |
なし |
米原亮三 |
|
第2回 |
2/22(火) |
第1章/禅の予備知識 *概要、下記参照 |
第1章/禅の予備知識 |
水野聡氏 *前回2021年の受講者(会場・Zoom・動画受講)が本講義を再度聞く場合は、受講料を減免する。 |
|
|
第3回 |
3/22(火) |
第2章/禅と美術① *概要、下記参照 |
第2章/禅と美術 |
||
|
第4回 |
4/26(火) |
第2章/禅と美術② *概要、下記参照 |
|||
|
第5回 |
5/24(火) |
第3章/禅と武士① |
第3章/禅と武士① 第3章/禅と武士② |
||
|
第6回 |
6/28(火) |
第3章/禅と武士② |
|||
|
第7回 |
7/26(火) |
第3章/禅と武士③ |
|||
2022年前期 第3章 禅と武士①②③ のご紹介
「武士は桜の花の如く、死に際していさぎよく散るべきである」。
学問や芸道のいずれの分野にも属せず、しかし一番色濃く日本文化を代表するのが武士道ではなかろうか。大拙はまず、日本に禅と武士道が生まれ、歩調をそろえて発展していった、その歴史的同期性に着眼しつつ、“生死を離れ”“今を最大限に生き切る”不屈の精神性を基調低音として、禅と武士の相関を様々なテキストを駆使して語り尽している。
北条氏をはじめとする鎌倉武士とは何か。そして戦国期の二大英雄、上杉謙信と武田信玄の生きざまとはどのようなものであったか…。さらに、武士以上に毅然として豪火の中に入寂した禅僧、快川和尚の軌跡をたどっていく。
武士道なくして、日本に禅なし。
禅なくして、日本に武士道なし。
≪1.禅と武士は、なぜ結びついたのか≫
歴史的に見て、仏教はかつて戦と関係しなかった。なぜ、禅だけが武士の戦う精神と結びついたのか。
①禅は道徳と哲学の2つの方面から武士を支援した。
道徳:一度道を踏み出したら、禅は決して振り返らないことを教えるから。
哲学:禅は、生と死を切り離して考えないから。
禅は意志の宗教だから、哲学よりもいっそう道徳的に武士道精神に訴えるのだ。
【学びのポイント】 宗派による教義の違い
・易行、他力 → 浄土宗
・難行、自力 → 禅
②禅は単純、直截、自恃、克己的である。
戒律的な傾向が武人の精神とよく合致する。立派な武士は禁欲的、自粛的である。
↓
武田信玄、上杉謙信 (葉隠武士道)
③禅と武士がともに発展した、歴史的必然性があった。
旧仏教が支配する京都ではなく、北条氏が拠点とした鎌倉には、貴族や旧仏教の地盤がなく、禅と武門はともに発展し、様々な日本文化成立の影響力となりえた。
④禅は武士のみならず、どのような新しい層とも柔軟に結びつく
・禅は特別な理論や哲学を定めない
・すなわちどのような考え、信条とも相容れる
・禅はいつも革命的精神の支援者である
「天台は宮家、真言は公卿、禅は武家、浄土は平民」
(平田篤胤「天台天子、公家真言」より)
≪2.北条氏と禅の結びつき≫
[1.北条時頼]
北条家の最初の参禅者は、五代執権北条時頼である。
京都から鎌倉へ禅僧を招く。さらに中国からも高僧を招いて禅の奥義を会得した。
・時頼の師: 中国の禅僧、兀庵普寧
[2.北条時宗]
・時頼の次男、第八代執権北条時宗は、日本が生み出した中世最大の偉人。
執権在職中に日本最大の危機である「元寇」に立ち向かい、これを撃退した。
元寇で戦死した日中両国の兵士を弔うため、仏光国師(無学祖元)を招き、円覚寺を開山した。
仏光国師と時宗の問答は、時宗の禅に対する丹誠をよく理解させる。
時宗:いかにして、我が諸々の思念と意識を断ち切れますか。
仏光:座禅を組め。時宗自身に属すると思う、一切の思念の源に徹底せよ。
時宗:私は俗事がたくさんあります。瞑想の暇が見つかりません。
仏光:俗事に携わろうとも、それを内省の機会として取り上げよ。いつかは汝の内なる時宗の誰であるかを悟るであろう。
時宗は、禅により国難を退けた、偉大な精神をもつ修行者であっただけではなく、後世、室町時代に最盛を迎える、日中貿易の端を開いた最初の権力者でもあった。
※フルバージョンは以下のPDFにてお楽しみください。
お申し込み
以下の【申し込みカート】より、ご希望の日時と受講形態を選び、『カートに追加』で受講券をお求めください。右上にカートの内容が掲載されますので手続きを進めてください。
決済はクレジットカードまたは銀行振込をお選びいただけます。
銀行振り込みをお望みの方は、受講券確保後、下記の口座にお振込みください。
※Paypalでのお支払い時に不具合が発生しましたら、こちらのPaypal問合せページ、
または0120-271-888までご連絡をお願い致します。
みずほ銀行 丸の内中央支店(004) 普通預金 1131101
トクヒ)ニホンブンカタイケンコウリュウジュク
2022年8月~2022年1月 後期のお申込
第8回禅と日本文化 Zoom無料体験
水野聡先生と読む、名著「禅と日本文化(鈴木大拙著)」。2022年後期初回の第8回授業(8月23日)をZoom無料体験できます。下記よりお申込みください。
(税込)
「禅と日本文化」講読会 2022年後期 6回一括申込(会場受講・Zoom・見逃し配信)
長期優待制度をご利用いただけます
会員の皆様は、在籍年数により長期優待をご利用いただけます。2022年年会費のご納入がお済でない方は、併せてお手続きください。
※優待適用可否、適用可能金額はこちらでご確認ください。
2022年2月~7月 前期 見逃し配信でまだ視聴できる
前期7回の見逃し配信視聴期間は、2022年12月31日までです。
【初受講】
IJCEE会員 9,000円
フレンドシップ団体・TJスクール生 11,000円
一般 12,500円
【再受講】※2021年実施の「禅と日本文化」講座4回シリーズを受講された方(受講回数は問いません)
IJCEE会員 6,400円
フレンドシップ団体・TJスクール生 6,600円
一般 6,800円
「禅と日本文化」講読会 2022年前期 動画配信
◎フレンドシップ券でお申込の方は、メモ欄にご所属団体名を必ず明記ください。
<フレンドシップ団体リスト>
HoTGIA(北海道通訳案内士協会)、N.G.A(新潟県通訳案内士協会)
GICSS(通訳ガイド&コミュニケーション・スキル研究会)、
KIGA(一般社団法人 関西通訳・ガイド協会)、HIGA(一般社団法人 ひろしま通訳・ガイド協会)
K-iTG(九州通訳・翻訳者・ガイド協会)、OIGA(沖縄通訳案内士会)
キャンセルポリシー
1) 講座開始の15日前まで:キャンセル手数料500円
2) 14日前から3日前まで:キャンセル料20%
3) 前々日以降:キャンセル料50%
4) 前日以降:キャンセル料100%
講師紹介

◆水野聡氏
古典翻訳家、中世日本文化史講師。
能、茶道、日本庭園、武士道、俳諧、禅など日本の中世の芸道、美学、精神文化を専攻。これら古典名著を現代語訳にて執筆、発刊しています。
オフィシャルホームページ【言の葉庵】では、自著を中心に千利休、世阿弥、一休宗純、宮本武蔵、松尾芭蕉等の名言名句を解説、紹介。いにしえの偉人、達人から、今日本人として美しく、強く生きるための知恵を学び、広く普及させるため、全国カルチャーセンターにて各講座を開講している。古典名著により親しむための丸秘原典読解教室も展開中。
著書に「強く生きる極意 五輪書/宮本武蔵著 水野聡訳(PHPエディターズグループ2004.8)」、「現代語訳 風姿花伝/世阿弥著 水野聡訳(PHPエディターズグループ2005.1)」、「南方録 現代語全文完訳/南坊宗啓著 水野聡訳(能文社2005.12)」、「葉隠 現代語全文完訳 山本常朝/田代陣基著 水野聡訳(能文社2005.12)」等がある。
会場受講
●IJCEE関東本部 機械振興会館内 *当日、本部前に貼り出すスケジュール表をご覧ください。
機械振興会館
◆〒105-0011
東京都港区芝公園3-5-8 本館B109
◆最寄りの交通機関
・東京メトロ日比谷線:神谷町駅下車 徒歩8分
・都営地下鉄三田線:御成門駅下車 徒歩8分
 新日本通訳案内士協会/NPO日本文化体験交流塾(IJCEE)
新日本通訳案内士協会/NPO日本文化体験交流塾(IJCEE)